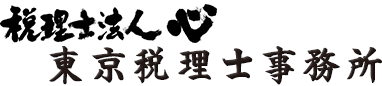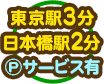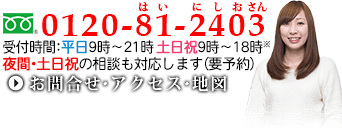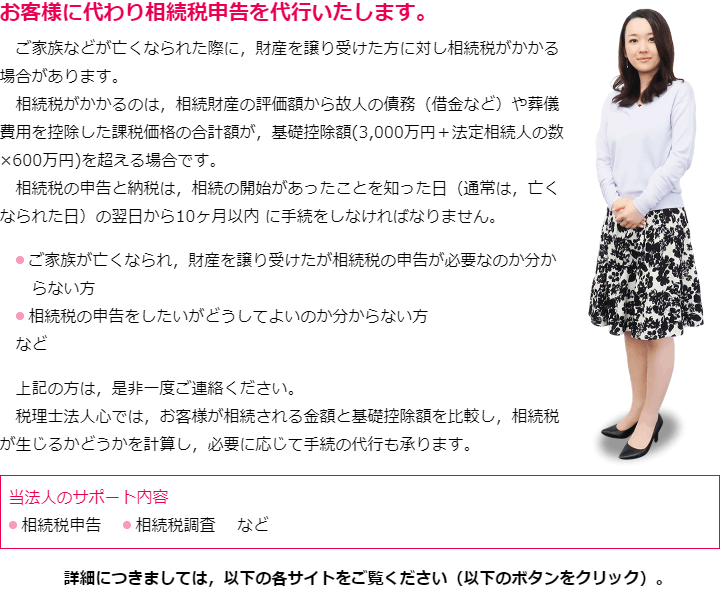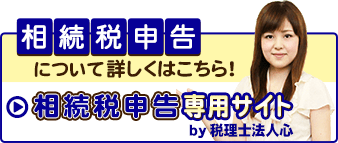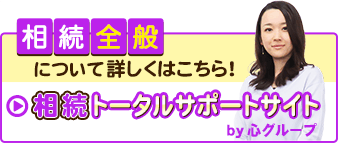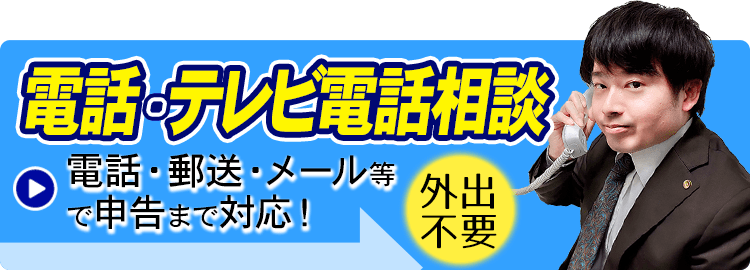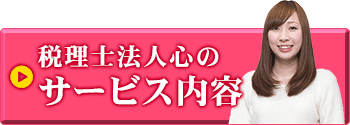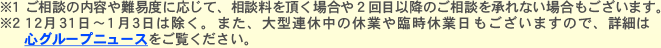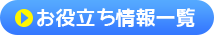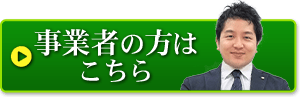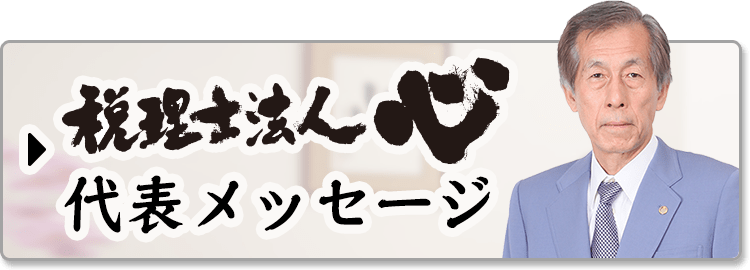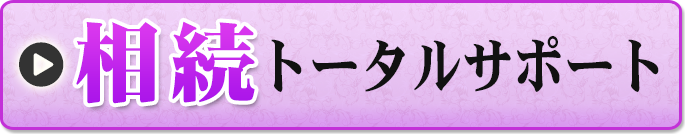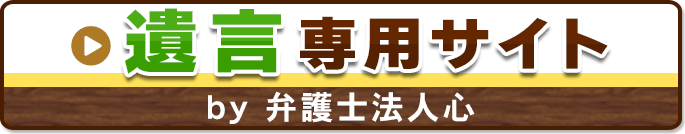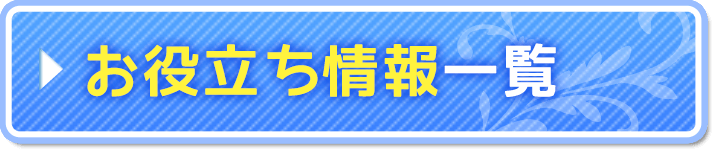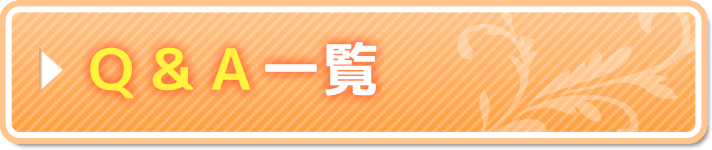相続税申告(相続発生後)
相続税の申告が必要なケース
1 相続税の申告が必要なケース

相続税の申告が必要かどうかは、亡くなられた方の課税される相続財産が基礎控除額を超えるかどうかによって決まります。
この基礎控除額は、 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)という計算式で求められます。
例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は 3,000万円 + (600万円 × 2) = 4,200万円 となります。
この金額を超える相続財産がある場合に、相続税の申告が必要となります。
基礎控除額の計算において重要なのは「法定相続人」の数です。被相続人の配偶者は、常に法定相続人となります。
被相続人の子どもは第一順位の法定相続人となります。
子どもがいない場合、第二順位の被相続人の親が法定相続人となります。
親がいない場合、第三順位の法定相続人の被相続人の兄弟姉妹の法定相続人となります。
法定相続人の人数が多ければ基礎控除額が高くなります。
2 相続税の申告と相続財産の範囲
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産に加え、みなし相続財産があります。
プラスの財産とは、具体的には不動産(土地や建物)、預貯金、株式・債券・投資信託、事業用資産、その他動産(金、自動車、宝石など)、が挙げられます。
マイナスの財産とは、具体的に、借入金やローン、未払いの医療費や固定資産税などの税金、葬儀費用が挙げられます・
みなし相続財産とは、生命保険金、死亡退職金、また、死亡する3~7年前以内に被相続人から贈与を受けた財産も、相続財産として合算される場合があります。
なお、生命保険金及び死亡退職金は一定の非課税枠があります。
3 基礎控除額を超える場合の申告義務
基礎控除額を超える財産がある場合、たとえ特例の適用により、実際に相続税が発生しない場合でも申告は必要です。
たとえば、基礎控除額を超える財産があっても、被相続人の自宅や貸し付けている土地の評価額を下げる小規模宅地等の特例の適用、一定金額まで配偶者の税額が軽減される配偶者の税額軽減の適用により、税額がゼロになることもあります。
ただし、これらの特例を適用するためには、相続税の申告が要件となるので、税額がゼロでも申告をしなければなりません。
4 相続税の申告と申告期限
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった翌日から10か月以内です。
この期限を過ぎると、延滞税や加算税が課される可能性があるため注意が必要です。
基礎控除額を超える財産がある場合には、財産の種類や特例の適用可能性を含めて慎重に計算し、期限内に申告を行うことが重要です。
また、複雑なケースでは税理士の助言を受けることが重要となります。
相続税を申告・納付する義務がある人
1 相続税と申告する義務がある人
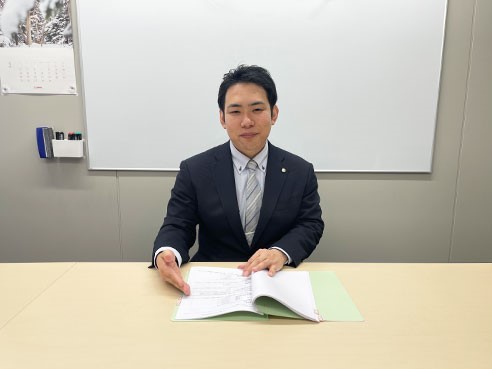
相続税の納税義務者は、基本的に、亡くなられた方から財産を取得した方です。
相続人の方は基本的に納税義務者に当たりますが、遺言書又は分割協議により遺産を受け取らないことになれば、納税義務者ではなくなります。
また、相続人でない方も遺言により遺産を受け取ることになれば、納税義務者にあたる可能性もあります。
そして、相続税の課税対象となり、申告する義務がある場合は、遺産の総額が基礎控除額を超えるかどうかで判断されます。
基礎控除額は、3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)という計算式で算出されます。
時々、遺産の総額ではなく、遺産の自身の受取額が基礎控除額を越えていなければ、相続税の申告が必要がないと勘違いしている方がいらっしゃるので注意が必要です。
相続税の申告は、相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に行う必要があるので注意が必要です。
2 相続税と納付する義務がある人
相続税の納税義務は、遺産の総額が基礎控除額を越え、特例等により、納付額の減額がない方にあります。
例えば、亡くなられた方の配偶者は、要件はあるものの、法定相続分又は1億6000万円の財産を受け取らなければ、配偶者の税額軽減の特例により、納税額が0円となります。
なお、 複数の相続人がいる場合、一部の相続人が相続税を支払わない場合でも、他の相続人が連帯して納付する義務があるので、注意が必要です。
相続税の納付は、申告と同じく、相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に行う必要があります。
3 相続税と税理士
上記のように相続税の申告と納税は期限内に、適切に行う必要があります。
特例が使える場合もありますので、相続税にお困りの方は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続税申告の費用
1 相続税申告の費用について

相続税申告書の作成のためにかかる必要は、大きく分けて2つあります。
1つ目は、相続税申告書を作成するため、また、税務署に申告書に添付して提出するための資料を集める際にかかる費用です。
まず、被相続人の戸籍を遡って収集する必要があるところ、役所にて戸籍発行のための手数料がかかります。
また、相続財産の中に不動産がある場合には、不動産を特定するための情報、所有者や所有割合の確認のため、土地評価のために法務局で、登記簿や公図等の取得が必要になり、発行のため手数料がかかります。
他にも、相続税申告のための資料として、預金の残高証明書、株式・投資信託等の有価証券の残高証明書の取得のために、証券会社や銀行に手数料を支払う必要があります。
さらに、上記の資料収集について、代理取得を依頼する場合には、更に士業に支払う報酬が発生します。
戸籍が転々としている場合や兄弟相続の場合には、集めるべき戸籍が大量にあるため、代理取得を依頼する方が多い印象です。
2つ目は、税理士に相続税申告を依頼した場合に発生する税理士報酬です。
この税理士報酬は、もちろん自分で申告書を作成して提出すれば、発生しない費用ではありますが、申告には専門的な知識が必要で、また、間違った申告をすると数年後に税務調査が来る可能性があるため、税理士に作成を依頼することをおすすめします。
2 相続税申告の税理士報酬の相場
インターネットでは、相続税申告書作成の税理士報酬として、遺産の1%前後と記載されているものが多いです。
ただ、実際には、税理士の報酬体系は、事務所ごとに異なり、遺産の1%以上の税理士報酬となる場合があります。
それは、次に述べるような、税理士報酬が加算されるような要素が多かったり、複雑な財産構成だった場合です。
3 加算報酬について
まず、相続税申告は、遺産額が多ければ、多いほど税理士報酬が高くなる傾向にあります。
これは、遺産額が多い場合には、それだけ高価な財産があり複雑な申告になる傾向があり、税務署からの指摘が入る可能性が高まるからだと考えられています。
また、相続人の人数が多ければ、税理士が説明をしなければならない人数が増えることになり、業務量が多くなることから、加算事由になることが多いです。
他にも、土地や非上場株式といった評価に計算が必要で時間がかかる財産がある場合には、それだけ税理士報酬が高くなります。
まずは、税理士事務所に問い合わせて、税理士と実際に話しをして、相続関係、財産構成等の内容を伝えて、見積もりを出してもらうことが重要です。